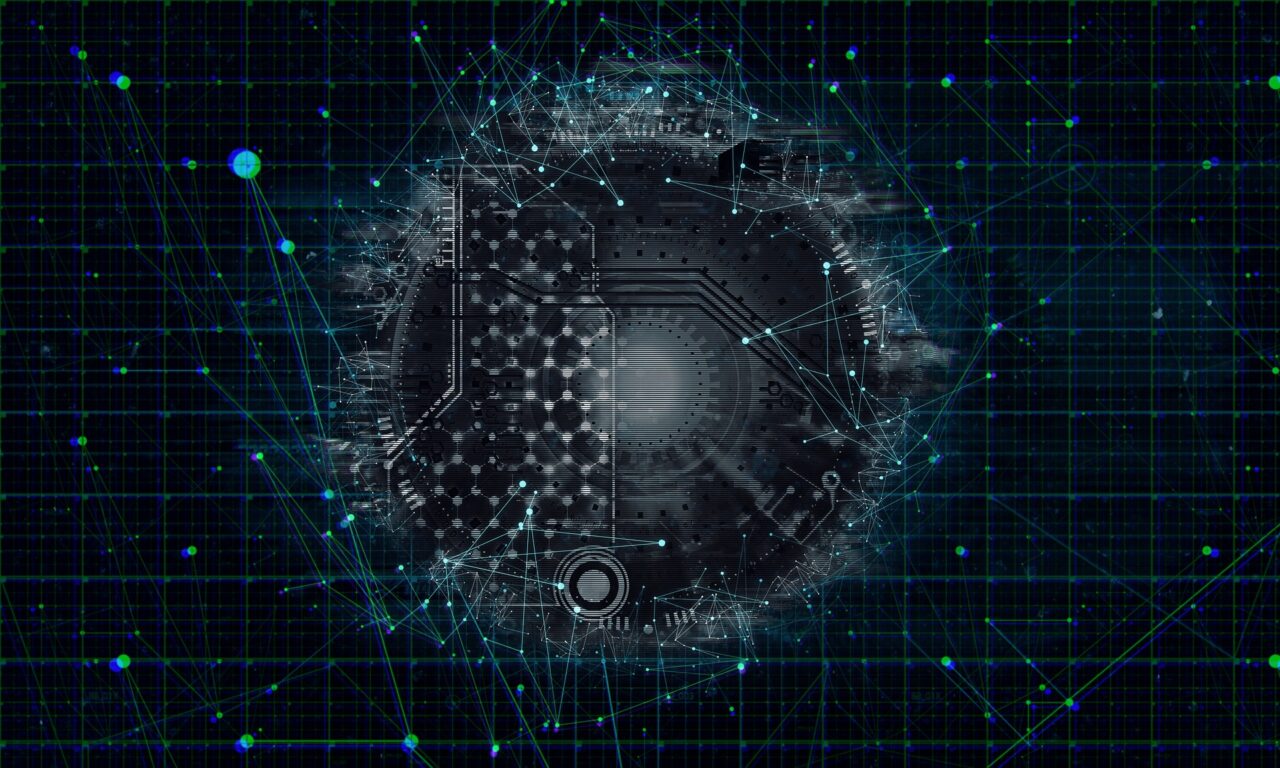KOMPASS話題のキーワード
現在の日本のポップシーンを代表するプロデューサーの一人となったYaffle。全曲を手掛ける藤井 風を筆頭に、iri、SIRUP、adieu、藤原さくらなどなど、数多くのアーティストの楽曲に関わる。その一方で、自身の名義では海外のアーティストのもとに赴いて共同で楽曲制作を行ない、グローバルな時代の音楽家のあり方を体現する存在でもある。
小学生からピアノをはじめ、高校では吹奏楽部に所属しながら軽音楽部にも顔を出し、ジャズとロックを浴びながら、音大ではアカデミックな現代音楽を専攻。小袋成彬とともにTokyo Recordings(現TOKA)を設立し、プロデューサーとして、アーティストとして活躍の場を広げてきたそのキャリアは、音楽に対する独自の哲学に裏打ちされている。
藤井 風の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』が大きな話題を呼び、自身がプログラムオーガナイザーを務める2022年5月の『TOKYO M.A.P.S』において初のライブセットを披露するこのタイミングで、Yaffleの現在地を紐解く。
Yaffle(やっふる)
TOKAのプロデューサーとして、藤井 風やiri、SIRUP、小袋成彬、Salyu、eill、adieuなどの楽曲を手がける。2020年9月、欧州各地のアーティスト計8名をゲストに迎えた1stアルバム『Lost, Never Gone』をリリース。国内外で高い注目を集める。2021年10月に発売されたポケモン25周年を記念したコンピレーションアルバムには唯一の日本人アーティストとして参加。映画音楽の制作も担当しており、参加した作品には『ナラタージュ』(2017年)、『響-HIBIKI-』(2018年)、『キャラクター』(2021年)などがある。
―Yaffleさんは数多くのアーティストの楽曲にプロデューサーとして関わる一方、ご自身の名義でも海外アーティストとのコラボレーションで楽曲を発表しています。Yaffleさんのなかでプロデューサーとアーティストの線引き、意識の違いなどはあるのでしょうか?
Yaffle:プロデュースとアーティストワークを意図的に変えているわけではないです。両方ともゴールはあまり変わらなくて、自分がいいと思うものをやるだけなんだけど、ただアーティストによって前提条件が違うので、完成するまでの道のりはバラバラです。「片やラグビー、片やサッカー」みたいな(笑)。「ボールを端に追いやる」という作業は変わらないけど、ルールが違うからアプローチも違いますよね。
―わかりやすいです(笑)。
Yaffle:だから、アーティストワークにしても、自分というアーティストに自分というプロデューサーが曲を書くという感覚は一緒です。ただ、自分単体としての履歴を見たときのコンテキスト、文脈的に意味があるものにしなきゃいけないとは思っていて。
クラウドに曲が上がるようになってから、聴ける曲数は気が遠くなるほど多くなってますよね。だから、ちゃんと自分で自分の意味づけをしていかないと、そこに飲まれそうになってしまいます。反響とか数字が前より見えやすくなってるのもあって、それも気にはしちゃうけど、そこに自分のモチベーションを置き過ぎると、どこかで折れてしまう。
―コロナ禍の約2年間のなかで、音楽との向き合い方に何か変化はありますか?
Yaffle:基本的にはスタジオミュージシャンなので、結局やってることはそんなに変わらなくて、そこにもどかしさはあります。社会は激変してるけど、自分の仕事はそんなに変わってないというか、むしろ増えたんですよね。ライブができなくなったぶん、みんなその時間で曲をつくるようになって、シンプルに仕事の分量は増えた。ある種の混乱期のなかで、自分のバイオリズム的には上向きになってる実感があって、そこにはミスマッチを感じています。
―「変わらない」ということにはプラスな部分もマイナスな部分も両方あると。
Yaffle:そうですね。変わらないことにも葛藤があります。ぼくが何かをして世の中がよくなるわけでもないというか。そもそも、音楽の効用で世界をどうにかよくしようというような思想にはあんまり賛成な立場ではなくて、「役に立つ音楽 / 役に立たない音楽」みたいな分類になるのは危険だと思うんですよね。
―社会が大きく変化するなかだと、そういう「効用」を求められがちではありますよね。
Yaffle:すべての職業の人が何かしら社会に対しての効用を求められる時代で、医療関係の人とかはその最前線にいるわけですけど、そうじゃない人たちも「社会性」みたいなことを求められるようになって。それはそれでいいことだと思うんですけど、それが行き過ぎると本質から離れていくと思っています。
本当は役に立たないのに役に立つ振りをすることも起こりえる。それよりは役に立たないなりにやっていくほうがいいと思うんです。もしかしたら、それがいずれ何かに役立つかもしれないけど、でもそれも意図してやることではないだろうと。
―コロナ禍で、音楽そのものの聴き方や捉え方の変化はありますか?
Yaffle:リモートワークの間に家事をしながらBluetoothで音楽をかけるような時間が増えて、漫然とかかってる音楽を聴くことが増えました。そうなったときに、いいサウンドシステムで向き合って聴いて効果的な音楽と、劣悪な環境でかけてもそれなりに「いい感じ」の音楽は構造的に全然違っていて、いまは時代的にも、自分の生活的にも、冗長性の高い音楽に惹かれることが増えたかもしれないです。
―「冗長性」というと、繰り返しなどの「余分」を含むことによって、一定のムードをつくり出すような音楽ということでしょうか?
Yaffle:ぼくの音楽家としてのキャリアはアカデミックなところから入っていて、たとえば「はじめの30秒を聴いてないと、後半のほうが意味不明」みたいな音楽に触れてきました。そういう音楽は、冗長性は低いですよね。
CMソングになるような、Aメロ、Bメロ、サビ、どこを聴いても同じムードで、でも一個一個の強度は高いような音楽は、シンプル過ぎる気がして以前は避けてたんです。でもそこに対してポジティブになってきた気がします。
対ポップミュージックということで言うと、昔から冗長性が高いものが求められていたと思うんですけど、そういう曲の技術的な困難さを知り、これはこれで難解な音楽をつくるのと同じくらい、すごくスキルフルなんだっていうことに気づいたんです。
―Yaffleさんが関わる楽曲の特徴のひとつに、音像の面白さがありますよね。一般的にJ-POPは中域に音が集まりがちですけど、中域は歌のためになるべく空けて、上と下を強く出すことで、独自の音像が生まれている。あらためて、サウンドメイクに関するこだわりをおうかがいしたいです。
Yaffle:ぼくの理想としては、なるべく要素が少なくて素晴らしければそれが一番すごいと思うんです。「緻密かつ複雑ではない」状態ですね。足せば足すほどオリジナリティーは出るけど、減らしてオリジナリティーを出すのは技術的に相当ハードルが高いので。
「J-POPとして聴いたことのある音像に近づけたら、チャート的に有利になるのではないか?」という根拠のない誘惑もあるにはあります。だから小森さん(エンジニアの小森雅仁)とよく話すのが、「トラックを追加するときにパソコンから警告が出てほしい」ということで(笑)。
―「音を抜く」ことを意識していると。
Yaffle:もちろん、ぼくもずっと東京で育ってきてるので、真ん中が団子になってて、それで「エモい」みたいに感じるのもすごくわかるんです。
でも、これまでと同じことを繰り返していても停滞感があるし、ちゃんと進化していくべきだっていう。ただ、そこもつねに葛藤はありますけどね。日本的なものに無理に変化を加えて、従来的な日本の価値観とは違うものをつくって、結局誰も聴かないと、それはただの自己満足になってしまう。一方で「真ん中に詰め込む」という価値観に対し、つねに「本当に必要ですか?」と自分に問い続けてもいます。
―自己批判を繰り返しながらも自分なりのアプローチを続けてきた結果、いま多くのアーティストから求められているという状況は、少しずつ聴き手の耳を変えてきた、聴き手の耳が変わってきたことの証明でもあるのかなと。
Yaffle:ぼくがそこに直接関わってるかはわからないですけど、少なくとも、J-POPというもの自体がよりよくなってるなとは、わりと確信めいて思ってます。「前がよくなかった」という意味ではなく、だんだんと積んでいくなかで、「いまはみんないいものをつくってるな」という感覚が、オーバーグラウンドにもアンダーグラウンドにもあるし、同じようなことを思ってる人がいっぱいいるんじゃないかとも思いますね。
―音像の話とも関連して、以前取材をさせてもらったときに「ちょっと前からポップミュージックは楽譜に記録できないところに移行している」という話になったのもとても印象的でした。
Yaffle:楽譜は音を二次元に書き起こすという意味では非常に便利です。他の民族音楽が口頭で伝えられたのに対して、西洋音楽は楽譜のおかげでちゃんと記録として残ったわけで。
ただ、楽譜から音が鳴るわけではなく、あくまで音響を書きとっているわけで、実際の音とは揺らぎがある。だからこそ再現芸術としてのニーズがクラシックにはあるわけですけど、その延長でモダンミュージックをやっても、そこに齟齬が出ると思うんです。
もともとは音を書きとめるためのツールだったのが、そこから逆転して、ツール越しに曲を書くようになることで、細かいアンサンブルの曲をつくれるようになった。転調とか変拍子、キーが複数あるとかです。でもその行きつく先は結局、現代音楽に代表されるような「無調」なんですよね。楽譜をデバイスとして使って曲を書いてるから、新しいことがその延長でしか生まれていません。
―そこからDAWの時代に移行して、より「音」の解像度が高まってるわけですよね。
Yaffle:DAWの音楽でも楽譜の感覚のままだと結局同じことで、たくさん転調して最後無調みたいなことになるわけで。でもそこには100年前に一回行って、結局一般的な聴衆はついて行けなくなってしまったんですよね。デバイス越しに見てる作家と、結果だけを聴く聴衆にずれが出てしまう。音楽教育をやりすぎると、そのデバイスがすべてだと思っちゃうけど、それは100のうちの10くらいを表したツールでしかなくて、いまは同じ「10」でも別の切り取り方があるように思います。
―それこそ音像や音響という切り取り方の「10」もあると。
Yaffle:ぼくの自己体験に落とし込むと、もともとはポップカルチャーが好きだったけど、でも自分が音楽の世界に本格的に飛び込んだのは音大からだったので、一回楽譜至上主義なところを通ってるんです。
でももともとは、音楽理論に特段詳しいわけではない人が基礎的なスリーコードでつくったような曲に憧れたりしてたから、こういう考え方になってるのかもしれません。なので、ビートメイクばかりやっていた人が突然、複雑な和声法に興味を持つとかも感覚としてはすごく理解できるけど、ぼくの場合はちょっと特殊なのかもしれないですね。
―ここまでの話を踏まえつつ、具体的に曲名を挙げながら話していただきたいと思うのですが、やはりいまのYaffleさんのプロデュースワークを代表する一人が藤井 風さんで、特に“きらり”はCMでのオンエアや『NHK紅白歌合戦』での歌唱もあり、代表曲のひとつと言ってもよいかと思います。あの曲がどのように生まれたのかをおうかがいしたいです。
Yaffle:ハウス影響下のJ-POPではあると思うんですけど、そうなりすぎないようにしました。ギターだけ生で入れてるんですけど、ハイブリッドなサウンドのバランス感覚はいつも研究し甲斐があるなと思います。
他の曲はつくっていくなかで、本人と話したり、わからないままやっていって、徐々に出口が見えてきたりすることもあるけど、この曲はCMのための書き下ろしだったこともあって、やりたいことがすぐにわかりました。ぼくのなかのイマジナリー藤井 風の「こうしてほしいんだろうな」っていうのが(笑)。
―イマジナリー藤井 風(笑)。
Yaffle:あとは、藤井 風さんの曲でコード進行を変えた唯一の曲でもあります。と言っても、そんな大げさなことではなくて、2番のサビのブレイクっぽいところ、一回上がって、落ちて、また上がっていくところを変えただけなんですけど。そこは「解決」とか「緊張」みたいな機能和声じゃなくて、もうちょっとドライな音像として必要だったので変えました。
―2番以降が単純な繰り返しではない構成になっているのもユニークですが、Yaffleさんは曲の構成にも関わっていたりするのでしょうか?
Yaffle:もともと長めのピアノイントロがあって、それは消したんですけど、歌がはじまってからは最初からこうでした。まあ、2番以降が違うと言えば違うんですけど、ぼくのなかでは「ヴァースの変形」くらいの捉え方です。逆に言うと、そう感じるようにビート側がしてるっていうのはあるかもしれない。
歌やピアノのコード進行、楽譜で書き起こせる部分はちょっと複雑性があるんだけど、後ろのトラックはむしろシンプルに聴かせるみたいな、そういう構造に落ち着いた気がします。
―ピアノイントロをカットしたとのことですが、歌とビートからはじまるのがすごく印象的です。
Yaffle:既視感の問題だと思うんですよね。マシュー・ハーバート(エレクトロニックミュージックシーンの鬼才)が「ピアノを前にするとこれまでの何千万というピアノ曲が頭に浮かんで何も書けない」と言ってましたが、それと同じでしょうか。
歌はじまりはいまのトレンドでもあると思うんですけど、長い歴史で見れば「イントロから歌」っていうはじまり方の曲を死ぬほど聴いてきたわけで、カウントもなくいきなり歌からはじまり、しかもビートが頭から完璧にある状態っていうのは、長い歴史で見たら新鮮な部類で、既視感は薄いはずです。
―音像的に声が近いようにも感じました。
Yaffle:歌の残響がない、ある種非自然的な状態にしているので、脳内にいるかのような感じに聴こえるっていう。そこは意図的な部分で、ぼくは音楽で異世界に連れて行ってほしいんですよね。映画でも小説でも、どこかに連れて行ってくれるようなものが好きで、そういう非日常性はつねに意識しているかもしれないです。ちょっと空間認知をずらして、いまの時間軸から切り離した聴取体験をしてほしい。
―サウンドメイクのこだわりがそういった空間認知のずれを生んでいると思うんですけど、iriさんがカバーした井上陽水さんの“東へ西へ”はパートごとに音の響きがガラッと変わって、非常にYaffleさんらしい作風だなと。
Yaffle:さっきまですごく残響してたのに、いきなり無響になるみたいなことって、日常生活では味わえないですよね。残響による空間認知はすごく面白くて、音楽のことが全然詳しくなくても、いまぼくがしゃべってる音声を聞いたら、風呂場なのか、吹き抜けのカフェなのか、狭いベッドルームなのか、大体どんな部屋にいるか想像できると思います。
これって言語化はできないけど万人がわかる感覚で、それをグチャグチャにしたいんですよね。ホールのような広い空間の音像をつくっておいて、いきなり無響になると、「急に一人」みたいな。ギャップ萌えみたいな感じですよね(笑)。
―いま話していただいたような発想が生かされている曲をプレイリスト『Yaffle Works』のなかからピックアップしていただけますか?
Yaffle:(実際にプレイリストをチェックしながら)iriさんの『neon』は頭の4曲の繋がりで空間認知をずらしてるようなイメージもあります。“はずでした”は音像が集まっておらず、ドラムだけやたら近くて、声は遠かったり近かったりして。やたら飛ばしたがる初期の3D映画みたいな感じですね。
Yaffle:Salyuさんの“Tokyo Tape”はバイオリンが映えるように空間を広くしています。音の高低も空間認識に関係していて、張り上げた声だと広い空間を想像するし、小さくて低い声だと狭い空間を認識します。ビート感も空間認識に関係してますし、ずっと続くような音は広い空間を錯覚したりもする。そういうものが渾然一体となっています。
―それこそ、楽譜には起こせない部分ですよね。
Yaffle:そうですね。楽譜に「リヴァーブ、オフ」とか書いても、それただのメモに過ぎないわけで(笑)。楽譜は音量変化に対しては解像度が低いんです。音程に関しては非常に解像度が高いのに、音量変化と、あとリリースタイミング、音が消えるタイミングも解像度が低い。
SIRUPの“Thinkin about us”も後半のアカペラになる瞬間にいきなり無響室みたいになって、そこから最後はバーンって広がる。SIRUPの顔が目の前にある状態で歌を聴くことなんて普通はないけど、そういう感覚も楽しんでほしいなと思いますね。
―最後に、Yaffle名義のアーティストワークについても聞かせてください。昨年12月に出た“Magic Touch”と、3月に出た“Wish You Could Come”は昨年10月にロサンゼルスで行なわれたライティングセッションに参加した際にできた曲だそうで。これまではヨーロッパでのコライトが多かったですが、なぜ今回はアメリカだったのでしょうか?
Yaffle:本場というと語弊があるかもしれないけど、そういう場所にも行ってみたほうがいいかなと思って。ロサンゼルスに行くのは、地方で生まれた子がギターを持って東京に行くみたいな感じに近いというか(笑)。そこには憧れもあるし、斜に構える自分もいるし、ないまぜでしたね。
―『Lost, Never Gone』の収録曲と比べて2曲ともビートが強調されていて、それはロサンゼルスという土地の影響を受けたものだと言えますか?
Yaffle:それはあると思うんですけど、でも環境的には「自助」でしたね。コミュニティーに何かを求めるというよりは、「自分で立て」みたいな感覚です。ロサンゼルスでは、どこかの文化圏にコミットしたというよりは、独立性みたいなものを感じたかもしれないです。
―Lost BoyやSATICAとのコライトはどんな部分が印象的でしたか?
Yaffle:とにかく作業が速いんですよ。Lost Boyなんて13時に入って、15時くらいに帰ったんじゃないかな。やっぱりお家芸な感じはありましたね。ワークフローができあがっていて、「誰かとスタジオで曲を書く」ということをずっと繰り返してきたからこそ生まれた文化だと思います。ある種システマチックで、完全にフローになってるんだなと思いました。
―ゴールデンウィークに開催される『TOKYO M.A.P.S』ではYaffleさんがプログラムオーガナイザーを務めているとともに、初めてのライブセットが行なわれます。今後はアーティスト活動もより積極的に行なっていくのか、あくまで『TOKYO M.A.P.S』というイベントありきのライブなのか、どちらが近いですか?
Yaffle:両方ですね。ライブをやりたいとも思ってたし、『TOKYO M.A.P.S』があったのも大きいし。自分のバイオリズムと、お話をいただいたタイミングがとてもいい感じに合ったので、ありがたいです。
そもそもが、実態の見えない、裏で手を引いてる人じゃなくて、単純に一ミュージシャンなんですよ。歌こそ歌わないですけど、ミュージシャンとしてやりたいことをやるだけです。なので、何か形態が変わったとしても、複数の職業を渡り歩いているような感覚ではなくて、いまはより自分の話をしたいタイミングだっていうことなんですよね。
TOKAのプロデューサーとして、藤井 風やiri、SIRUP、小袋成彬、Salyu、eill、adieuなどの楽曲を手がける。2020年9月、欧州各地のアーティスト計8名をゲストに迎えた1stアルバム『Lost, Never Gone』をリリース。国内外で高い注目を集める。2021年10月に発売されたポケモン25周年を記念したコンピレーションアルバムには唯一の日本人アーティストとして参加。映画音楽の制作も担当しており、参加した作品には『ナラタージュ』(2017年)、『響-HIBIKI-』(2018年)、『キャラクター』(2021年)などがある。
シェアする
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
引退から40年、山口百恵の600曲以上におよぶ楽曲がサブスク解禁
SNSギタリストの可能性 世界でバズを起こすIchika Nitoの歩み
NFTはアーティストの命綱になるか? MIYAVIとジェフ・ミヤハラが語る
世界的ゲームクリエイター小島秀夫のポッドキャスト番組がSpotifyで独占配信
藤井 風が世界中でバイラルヒット。Spotify年間ランキングから、日本のアーティストの躍進に迫る
Spotify×レコードの日。次世代を担うアーティスト3組に聞く、サブスク時代のアナログの魅力
佐藤千亜妃とさとうもかが考える音楽活動の「やり方」と「あり方」。TikTokのバズのその先で
新海誠『すずめの戸締まり』とタッグ。日本のアニメを世界につなぐ、Spotifyの想いを垣間見る

最新情報をチェックしよう!