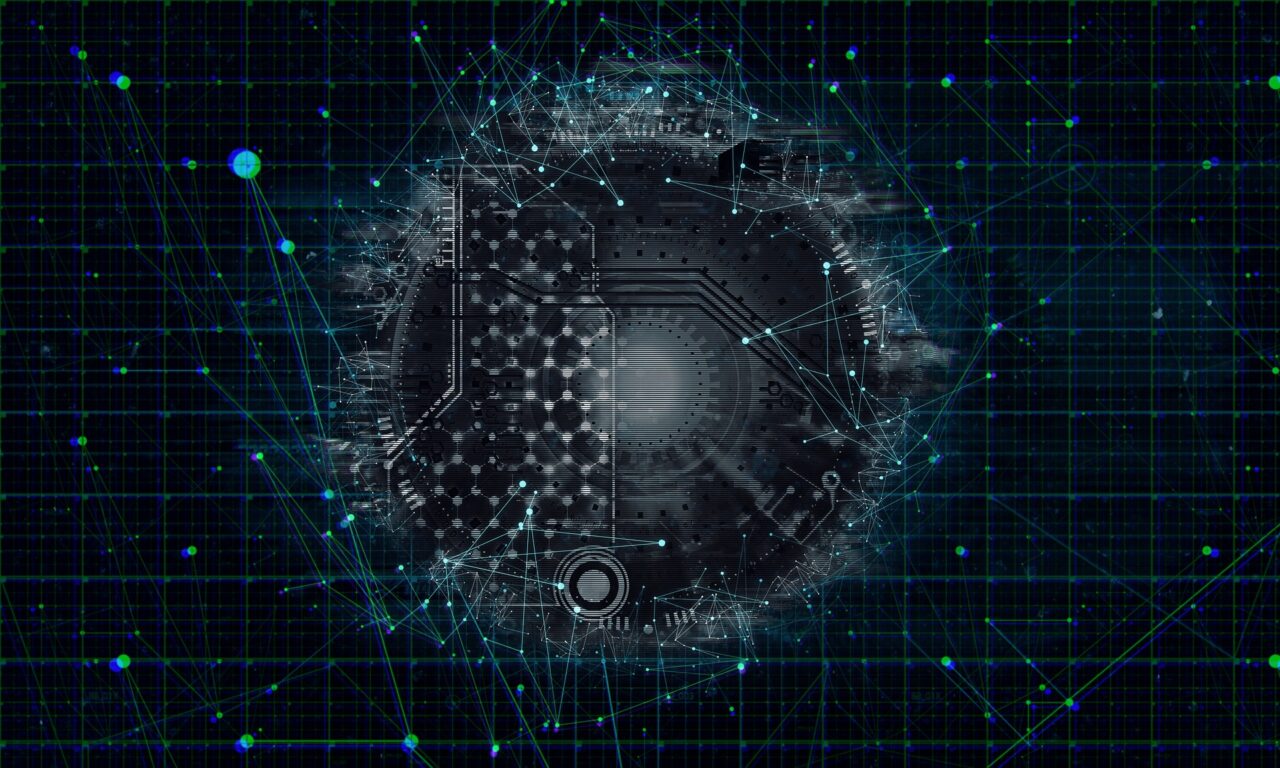次代を切り拓くデザイナーやアーティスト、ミュージシャンといった若きクリエーターたちにスポットライトを当てる連載企画 “On The Rise”。第5回目となる今回は、2019年の結成以降、主に東京のクラブシーンで活動するDJクルー Vinyl Youth(ヴァイナル ユース)をフィーチャーする。
2022年も半ばに差し掛かり、コロナ禍で約2年間続いた規制が徐々に緩和され、日本各地のクラブでは本格的にパーティが復活し始めた。東京ではオーガナイザーやDJ、客層も若い世代が台頭し、新たなシーンが形成されつつある。今回フィーチャーするVinyl Youthは、現在の東京クラブシーンの一端を担う新世代のDJクルー。メンバー全員が1999年生まれの若手でありながらも、彼らより上の世代のDJたちとも積極的に共演し、そのプレースタイルが支持を集めている。Vinyl Youthの各メンバーの音楽的背景や趣向はそれぞれ異なるが、クルーの通奏低音にあるのは、2000年代に台頭したDJ Harvey(DJ ハーヴィ)やIdjut Boys(イジャット・ボーイズ)、Rub N Tug(ラブンタグ)などに代表されるニューハウス~ディスコ・ダブといわれるジャンル。2000年代初頭の東京では、一部のファッション関係者やDJたちの間でこのジャンルに特化した独自のシーンが存在していた。本題に入る前に、当時のことを簡単に振り返りたい。
2000年前後のクラブシーンでは、Larry Levan(ラリー・レヴァン)やDavid Mancuso(デヴィッド・マンキューソ)などの伝説的DJたちが世界的な再評価を受け、彼らのプレーしていたダンスクラシックが注目され始めていた。そのプレイリストの中にはディスコやロック、ニューウェーブなどあらゆるジャンルの楽曲が混在しており、後に彼ら先人たちのダンスフロアに対する概念をさらに拡張し、ディスコ・リエディット文化を確立させたDJ Harveyやその遺伝子を受け継ぐIdjut Boysらの活動もあらためて評価されることに。2001年、アメリカ西海岸でDJ Harveyとウェアハウスパーティを行なっていた“Paul T.”ことポール高橋は、自身の主宰するストリートブランド〈SARCASTIC(サキャスティック)〉からMix CD『DJ Harvey – Sarcastic Study Masters』をリリース。このCDはコアなリスナーのみならず、その後世界のストリートシーンにも大きな影響を与えることになる。一方で東海岸に位置するニューヨークでは、元「Mo’ Wax(モ・ワックス)」のTim Goldsworthy(ティム・ゴールズワーシー)がJames Murphy(ジェームス・マーフィー)と「DFA Records(DFA レコーズ)」を設立し、世界的なポストパンク~ニューウェーブ・リバイバルのきっかけを作る。これらの動きと呼応するように、日本ではMOODMAN (ムードマン)や「Crue-L Records(クルーエル・レコーズ)」の瀧見憲司、川辺ヒロシらが自身のルーツであるニューウェーブや同様の質感を持つ新譜、異形のディスコをDJセットに取り入れるようになっていった。また、それまでヒップホップ・フィールドを中心に活動してきたForce Of Nature(フォース・オブ・ネイチャー)のKZA & DJ KENTも、同時期にディスコやハウスなどのダンスミュージックへと本格的に傾倒していく。2004年には〈Supreme(シュプリーム)〉のオリジナルクルーの1人であるAaron Bondaroff(エーロン・ボンダロフ)の主宰する〈aNYthing(エニシング)〉からMix CD『Rub N Tug Volume 1』がリリースされ、DJ Harveyの影響下にあるRub N Tugが台頭。2005年には〈STÜSSY(ステューシー)〉が主催し、Rub N Tugを筆頭にPaul T.、Force Of Nature、〈GIMME FIVE(ギミーファイブ)〉のMichael Kopelman(マイケル・コッペルマン)ら当時のシーンのキーパーソンたちが集結した「MAJOR BLADE TOUR 2005」が日本で行われた。このように、ファッションと音楽がリンクしたムーブメントとして盛り上がりを見せていたニューハウス~ディスコ・ダブも、2000年代半ばになると“エレクトロ”が東京におけるメインストリームのジャンルとなり、シーンとしては停滞期に突入する(*後に海外ではAlex Olson、日本ではMonkey TimersやYAMARCHYらがこの流れを引き継ぐ事になるが、本稿では割愛)。
Vinyl Youthの4人は、当時のシーンをリアルタイムで経験していないものの、先人たちのスタイルを自然に継承し、さらに新世代らしい視点も兼ね備えている。今回のインタビューでは、彼らの音楽的なルーツや現状のクラブシーン、そして今後の展望についてを気兼ねなく語ってもらった。これからのシーンを牽引する若き4人の言葉に、耳を傾けてみよう。
Vinyl Youth(左から Juddy, Kinya, Daichi, Kamome)
HYPEBEAST:まずVinyl Youthを結成した経緯を教えてもらえますか?
Daichi(以下、D):2019年ごろに僕とJuddyが江ノ島のOPPA-LA(オッパーラ)で一緒にパーティを主催していて、KamomeとKinyaも渋谷のオルガンバーでDJをやっていたんですね。
Kamome(以下、Ka):僕とKinyaはお互い文化服装学院の学生の時に出会って、オルガンバーで一緒にパーティをやっていました。僕は今DOMICILE TOKYO(ドミサイル 東京)というショップで働いているんですが、店長のYAMARCHYさんがよくOPPA-LAに遊びに行っていて、彼に連れられて頻繁に通うようになったんです。ある時、OPPA-LAのオーナーの和田さんが僕とDaichiが同い年であることを知って、2人を引き合わせてくれて。そのときにみんなとも知り合いました。Rub N TugのEric Duncan(エリック・ダンカン)のパーティだったよね?
D:そうそう。それまでもなんとなく見かけたことはあったけど彼を同い年とは思ってなくて、どんな音楽が好きなのかも知らなかったんです。で、Ericのパーティで紹介されて、同世代で同じような音楽が好きなやつがいるんだっていう(笑)。当時まだ同世代のDJがほとんどいなかったので、僕とJuddyはローカルのDJを集めてパーティを1~2年くらいやっていました。それは僕らがまだ若かったこともあって、学生ノリのパーティでしたね(笑)ジャンル的にはヒップホップ、R&B、ロック、ダンスミュージック……オールジャンルというか、まあなんでもかかる感じです。そうこうしているうちにだんだんDJを本気でやってみたいと思い始め、ダンスミュージックだけでパーティをやりたいと考えるようになりました。そんな時期にKamomeと知り合って、彼も同じ事を思ってたみたいで、じゃあ一緒にやろうとなったのがVinyl Youthの始まりです。
Vinyl Youthの名前の由来は、みんなレコード(ヴァイナル)でDJをやっていたから?
D:そうですね。今はデータも使ってるんですが、最初はみんなレコードだけでDJをやっていたんです。それでクルーの名前をつけるときに、“ヴァイナルで(DJを)やってる若い奴ら”って事でVinyl Youthになりました。
当時その年齢でレコードだけでDJをやってるのは珍しいですよね。そもそもダンスミュージックに興味をもつきっかけは何だったんでしょうか?それぞれの音楽的なバックグラウンドを含めて教えてもらえますか。
Juddy(以下、J):僕は高校1年生くらいのときに地元の古着屋の店員さんにStones Throw(ストーンズ・スロウ)周辺のヒップホップを教えてもらったのがきっかけで、そこから派生してエレクトロとか他のジャンルも聴くようになりました。
Kinya(以下、Ki):僕は中学校1~2年生くらいのとき、音楽に詳しいお兄さんのいる友達がいて、彼から2Pacとかを教えてもらってヒップホップにハマりました。ヒップホップを聴いているうちに曲の元ネタを探るようになって、そこからソウルとかディスコ~ダンスミュージックに拡がっていったんです。上京前はDJをやっていたわけではなかったんですが、レコードは集めてましたね。ターンテーブルを持ってる友達の家で聴いてました(笑)
D:僕は元々父親がバンドをやっていて、生まれた時から家にレコードがたくさんあったんです。だから自然な流れでレコードを手に取るようになりました。ダンスミュージックに関しては、18歳のときにOPPA-LAで働くようになったのがきっかけです。当初はヒップホップが好きで入ったんですが、お店でダンスミュージックを聴いているうちに、こういう音楽で踊れるなんて最高だなと思うようになって。それで家にあるレコードをあらためて見直すと、色々リンクすることがあって、さらに掘り下げるようになりました。
Ka:僕は元々服が好きで、高校生のときからYAMARCHYさんがオルガンバーでやっていたパーティに通っていて、そのことがきっかけで本格的に音楽に興味を持つようになった感じです。文化の学生になってからは、オルガンバーやOPPA-LAで毎日のように遊ぶようになって、DJもやるようになりました。
それぞれダンスミュージックへの入口が異なるわけですが、それがなぜ4人とも共通して2000年代初頭の東京で流行っていた所謂ニューハウス~ディスコ・ダブみたいな音楽が好きなんでしょうか?また、先日の現場(*KOARA~MITSUKI)をみて、今の東京の若い世代にもそういったジャンルの音が浸透しているのかなと思ったんですが。
Ki:それはYAMARCHYさんの功績じゃないですか(笑)僕がOPPA-LAに行ったのも、彼に連れていってもらったのが最初だし。Eric Duncanを観たのも、その時が初めてでしたね。
Ka:どうなんだろう?僕らはEricとかIdjut Boysとかの海外DJのプレーを生で聴けたっていうのも大きいと思います。
Ki:OPPA-LAっていうお店のカラーもあるんじゃない?傾向としてその手のジャンルに強いから、自然と好きになると思う。
D:うーん……でも僕はあんまり(ジャンルを)意識していたわけではないかな。OPPA-LAで働いていて、日々色んなパーティがあるわけですけど、自分の中にスッと入ってきたのがたまたまIdjut Boysとかの音だったというか。でも僕ら以外で、同年代でそういった音楽が好きな人ってあまりいないですよ。やっぱり他はテクノとかヒップホップが多いと思います。
Ki:渋谷にMITSUKI(翠月)ができてから少し変わったんじゃないかな。例えば週末のMITSUKIでディスコなんかをかけてると、遊びに来たお客さんが知らないジャンルでもプレーが良ければ盛り上がるというか。
なるほど。今日は4人のルーツを探るべく、影響を受けたレコードやモノを持ってきてもらいました。それぞれ解説してもらえますか?
Ka:まずトランペット奏者 Herb Alpert(ハーブ・アルパート)の『Rotation』の12インチ(A&M Records、1979年)です。超有名なダンスクラシックの名盤で、現場でもよくかけていました。このクリアヴァイナルは割とレアで、今はどうかわからないんですが、僕が買った当時は結構いい値段だったんです。それまで値段の高いレコードを買ったことなかったので、そういう意味でも思い入れのある1枚。次はYAMARCHYさんから直伝されたRub N Tugの2LPコンピ『Rub’ N’ Tug Present Campfire』(Eskimo Recordings、2005年/ *CD盤はMix CD)です。これは今でもたまに現場で使ってますね。最後は『Luxxury Reworks Volume 2』(Expensive Sounding Music、2020年)というエディットシリーズで、B面にはDJ HarveyがミラノのBoiler Roomでプレイした曲のリワーク(I’m Petula)が入っています。朝方にかけると最高に気持ち良くて、自分の中でも特に好きな1枚です。
D:僕の1枚目は父親から貰ったBeastie Boys(ビースティ・ボーイズ)のアルバム『Check Your Head』(Capitol Records、1992年)で、初めて自分のものになったレコードです。僕がDJをやるかやらないかって時期に、勝手に家にあったターンテーブルをいじってたらくれました(笑)。子供の頃からこのアルバムは家で流れてたので、歌詞の意味は分からなくても曲は自然と口ずさめますね。その流れで2枚目は、好きなBeastie Boysの曲 An Open Letter To NYCをRub N Tugがリミックスした12インチ(2006年の再発盤、*オリジナルは2005年)。3枚目はTodd Terje(トッド・テリエ)のアルバム『It’s Album Time』(Olsen Records、2014年)で、僕が初めて買ったレコードです。当時は学生だったので、2LPで値段も高かったんですけど、頑張って買った大事な1枚ですね。
Ki:僕はレコードじゃなくて本を持ってきました。まず雑誌『STUDIO VOICE(スタジオボイス)』の2006年6月号(プログレッシヴ・ディスコ特集)。これを手に入れたのは少し前なんですけど、買ってしばらく経ってから読み返すと、DJ HarveyやRub N Tug、Force Of Nature、瀧見さんとか知ってる固有名詞がいっぱい載ってることに気付いて(笑)自分的にダンスミュージックの教科書のような内容なので、今見ても面白いです。次も雑誌で『relax(リラックス)』の2000年12月号。Mo’ WaxというUKのレーベルの特集で、オーナーのJames Lavelle(ジェームス・ラヴェル)や関係者のインタビューに加えて、Futura(フューチュラ)のアートワークとかSkate Thing(スケートシング)さんのグラフィックも載っているのがアツいですね。音楽から離れますが、2000年に出版された『Messengers Style』という写真集は、当時のニューヨークのメッセンジャーのリアルなスタイルが紹介されています。僕はファッションも好きなので、中を見るとCarhartt(カーハート)のパンツをカスタムしてクラスト仕様にしているのとかヤバいな~って発見があったり。次はLarry Clark(ラリー・クラーク)監督の映画『KIDS(キッズ)』(1995年)のパンフレット。この映画は学生の時に観て、1990年代のカルチャーを象徴する作品として影響を受けました。最後は好きなニューヨークのアーティスト Weirdo Dave(ウィアード・デイヴ)の『Fuck This Life』(2008年)というZINEです。作品集は高いんですが、ZINEなら安いし(笑)、紙もチープなんですけど、中のアートワークはカッコいいです。
J:僕は好きなレーベルのレコードを2枚持ってきました。1枚目は1980年代にDJ Harveyとイギリスでパーティをやっていて、90年代はWicked Sound Systemというクルーに所属していたDJ Garth(DJ ガース)の主宰するレーベル Greyhound(グレイハウンド)から、Markie Mark & Garth Feat. Nkosazanaの12インチ『The Price』(2003年)です。この曲のように当時のニューディスコとかディスコ・ダブシーンでかかってた煙たい感じのディスコが好みです。最近ではあまりこういう雰囲気の曲はないですよね。2枚目は1990年ごろにイギリスで設立されたHooj ChoonsというレーベルのParks & Wilson『Feel the Drums EP』(2000年)です。ジャンルはプログレッシヴ・トランスなのかな。このレーベルは2003年に倒産したんですが、その後2007年ごろに復活したんです。でもその後しばらく活動が止まってて、最近また動き出したみたいで再発が出てるんですよ。型番が150くらいあるので、全然集められてないんですけど(笑)。こういったクラシックなトランスも好きで、現場でも使いやすいので割とその辺のジャンルもディグしていますね。
ここからはVinyl Youthについてお聞きします。クルーとして初めて主催したパーティについて話してもらえますか。
D:2019年の6月にDISKO KLUBB(ディスコクラブ)のYAMARCHYさんとGYAOさんをゲストに迎えて、OPPA-LAで行ったのが最初ですね。熊本のIwakiriさんというDJにもサポートに入ってもらって、オールナイトでやりました。先ほども言いましたが、Juddyとは以前から一緒に遊んでいたんですけど、2人(KamomeとKinya)とは知り合ってから間もない時だったので、全員がまだそんなに仲良くない状態で臨んだパーティでした(笑)だから最初はお互いどんなプレーをするのかも分からなかったですね。
Ka:明け方にFran-Key(フランキー)さんがいきなりフラッと来たんです。彼がOPPA-LAで売っているKZAさんセレクトのレコードの中から何枚かピックして、突然ブースに乱入してDJをやり始めて(笑)
D:あれはみんなブチ上がったね(笑)。ヤバかった。
J:俺レコードもらった(笑)。
Ki:初回からミラクルが起きたよね。その後渋谷のKOARAでVinyl Youthのレギュラーパーティが決まって、それからは毎月やるようになりました。
フライヤーのアートワークも印象的ですね。これは誰が担当してるんですか?
Ka:フライヤーのアートワークは全部Daichiが手掛けています。周りの大人から結構評判良いんですよ。
D:でも今見ると最初のフライヤーひどいね(笑)。今までのパーティのフライヤーで、ちゃんと印刷したのはこれしかないですね。KOARAでレギュラーをやるようになってからは、毎月フライヤーをその都度デザインしています。
デザイン面では何から影響を受けたんですか?
D:具体的に何かから影響を受けたとかはないですね。レギュラーパーティでは毎回誰かしらゲストを呼んでいるので、そのゲストに合わせてデザインしています。あとはそうですね、4人のキャラクターをイメージしたらなんとなくデザインの方向性が固まっていった感じです。
今の時代ってコレクティブとかDJクルーって結構活躍してると思いますけど、国内外問わず参考にした人たちっていますか?
全員:いないです(笑)。
Ki:例えば、先輩ですけどCYKの存在とか当時は全く知らなかったです(笑)。僕らは活動当初はそれくらい無知だったので、特に誰を目指しているとかもなかったですね。
そうなんですね(笑)。4人の中で役割分担とかはあるんでしょうか?
Ka:特に明確にはないんですが、Kinyaがとりあえずムードメーカーで、Juddyは結構アンダーグラウンドでドープな曲をかけるというか。僕とDaichiは割と全体の流れを作る感じかもしれないですね。あと、僕はひたすら(DJの)現場に出ていました。今もですけど。
Ki:Kamomeがフロントマンというか、現場で僕らの名前を広めてくれたおかげで、色々な方面から声がかかるようになって。それはありがたいですね。
KOARAでレギュラーパーティを始めてからは、クルーとしては順調にステップアップしていった感じですか?
Ki:最初からお客さんは少なくはなかったよね?
D:確かに全然入ってないとかはなかったですね。
Ki:1回目はさすがにあまり多くなかったかなとは思いますけど、レギュラーをやり始めてからはお客さんがだんだん増えていった感じです。
D:嬉しかったのは、毎回来てくれるリピーターの方が増えていったことですね。
お客さんの年齢層はどんな感じですか?
D:同世代とか年下が多いんですが、あとは上の世代の方がフラッと来てくれることもあり、幅広いと思います。
皆さんまだ20代前半ですけど、それぞれが上の世代の方々と頻繁に共演している印象があります。それはどうしてだと思いますか?
Ki:単純に僕らがその人たちのDJが好きだからじゃないですか(笑)。
D:実際、僕らは先輩たちのパーティによく遊びに行っていましたし。それで自分もDJとして現場に呼んでもらったりして、良くしてもらっています。特に大人と共演したいって思っていたわけではなくて、好きなDJがたまたま上の世代に多かったってことですかね。好きな人たちから色々吸収して勉強したいなと思ってます。
これまでVinyl Youthとして約3年間活動した中で、特に印象に残っているパーティはありますか?
D:僕はMITSUKIでやったVinyl Youthの結成1周年パーティかな。
Ka:そうだね。僕らの1周年パーティをKOARAとMITSUKIの2箇所でやったんですよ。
Ki:最初KOARAでやって、キャパオーバーになるくらいメチャメチャ人が入って。
D:KOARAにあんなに人が入ってるの初めて見た(笑)。もしかしたら過去にはあったかもしれませんが、僕らはそれまでKOARAであの人数は経験したことなかったです。その後のMITSUKIはどうなるかなと思ったんですが、そっちにもかなりお客さんが来てくれて。MITSUKIの方はDISKO KLUBBの面々を全員ゲストに呼んで、集客もすごいことになって、売り上げも更新しました。
Ka:内容も良かったよね。変な感じで盛り上がってるパーティではなく、雰囲気も流れも良かった。
Ki:本当に良いパーティだったっていうのが目に見える感じでしたね。
D:それまで1年間やってきて、自分たちが積み上げてきたものが、実際のお客さんの数で目に見えて実感できたというか。「こんな感じなんだ」っていう。達成感もあったんですが、もっとこれから頑張らなきゃっていう気持ちになりましたね。
VINYL YOUTH(@vinylyouth_)がシェアした投稿
Ki:あと僕的には、今年の4月23日(土)に行われた渋谷 contact(コンタクト)の6周年パーティがハイライトかな。
D:元々そのパーティはDJ Harveyも出演する予定だったんですけど、来日できなくなって、僕らがメインフロアのトリを担当したんです。フロアも満員で、人生で初めてあんな大人数の前でDJしましたね。
Ki:でもみんな意外と臆することなく、のびのびできたのが良かったよね。
Ka:本来1時間半の予定だったのが、なんだかんだで2時間くらいプレーしてたしね。楽しかった。
昨年にはVirgil Abloh(ヴァージル・アブロー)のOff-White™ Imaginary TVにも出演しましたね。これはどういった経緯で出演が決まったんでしょうか?
Ka:あれはオカモトレイジさんが僕らの事を野村訓市さんに推薦してくれたみたいで。それ以降MILD BUNCHのパーティにも呼んでもらえるようになりました。
Ki:VirgilからDJ中にインスタのストーリーにメンションが来てたみたいなんですが、僕らプレー中は一切見てなかったので全然気づかなくて(笑)
D:彼が生きてたら今ごろ来日してるだろうし、もしかしたら会えたかもね。一緒にDJできたら良かったですね。
Off-White™ Imaginary TV(@off___white___imaginary___tv)がシェアした投稿
今の東京のクラブシーンについてはどのように見ていますか?
Ka:シーン全体のことはよく分からないですけど、最近あらためて思ったことは、僕にとって同い年でガッツリ遊べるのはこの3人くらいしかいないってことかな。もちろん他にもたくさん友達はいるんですが、同じテンションで遊べないというか。
D:好きな音楽の範囲が被らないってことだよね?それは僕もそう思う。僕らが知らないだけかもしれないですけど、本当にいないよね。逆にカッコいい同年代のDJがいたらテンション上がりますし、一緒にやりたいと思いますね。
Ki:仲間を引き入れて、ASAP MobみたいにVinyl Youthを組織化して大きくするとかね(笑)
それぞれが同世代の人たちがやっている別のパーティに遊びに行くことってあるんですか?
D:うーん……どうだろう?そもそも同世代で僕らのようなことをやってるパーティがほとんどない気がします。
Ka:自分たちの好きなジャンルの先輩たちがやっているパーティに遊びに行くことが多いかもしれないですね。
Ki:僕はいろんな界隈のパーティにたまに顔を出したりしていますけど。何の約束もせずにクラブで3人とたまたま遭遇することはありますよ(笑)。
D:あとは誰かが別の現場の時に遊びに来てくれたりとかね。
Ki:先ほども少し話しましたけど、同世代だとテクノとかヒップホップが多くて、僕らみたいなディスコをかけるパーティはないですね。なので、かかる音が好みであれば世代関係なく遊びに行く感じです。
地方のシーンについてはどうでしょうか?
Ka:地方はレコード文化が根強くて、ヴァイナルだけでDJをやっている同世代の友達は結構います。
D:東京に比べて、ジャンルがあんまり細分化されていない印象があります。例えばディスコ、ハウス、テクノ、ベースなどの各ジャンルに特化しているわけではなくて、それらが1つになったパーティが各地にあるというか。お客さんが特定のジャンルめがけて遊んでいる感じはしないですね。
KamomeさんとDaichiさんはVinyl Youthとは別にOpus.という別名義での活動もしていますよね。これはどういったユニットなんでしょうか?
Ka:コロナ禍の自粛期間に職場も休みで時間がたっぷりあったので、僕は1人でよくOPPA-LAに遊びに行っていたんです。もちろんお店は営業していなかったんですが、Daichiに鍵を開けてもらって、お客さんがいない中で、昼から次の日の朝まで2人で延々バック・トゥ・バックをやっていて(笑)。そうやって色々なプレーを試しているうちに、Vinyl Youthとは別に実験的なユニットをやっても面白いかなと思ったのがOpus.を始めたきっかけです。
D:OPPA-LAで2人で回している時に、同時にインスタライブもやっていたんです。あと、これまでも僕とKamomeの2人でDJに呼ばれることがたまにあったので、だったらユニット名をつけておこうかなと。Opus.は、僕の中ではVinyl Youthとはまた全然別の位置付けですね。
具体的にはVinyl Youthでの活動と何が違うんでしょうか?
D:Opus.は、Vinyl Youthの中の2人がやってるユニットと受け取られるかもしれませんが、僕の中ではまた全然別の位置付けですね。一緒にやってるKamomeがたまたまVinyl Youthのメンバーだっただけで、たとえ彼が別のクルーにいたとしても、Opus.は彼と組んでいたと思います。
Ka:Vinyl Youthだと、音楽的にはやっばりディスコが根底にあるんです。それに対してOpus.は、音楽的な方向性が全く違います。
D:これまでOpus.名義でオールナイトロングを3~4回くらいやっていて、アシッド・テクノやスノーなテクノとかをかけたりしました。とにかくパーティのオープンからクローズまでを全て自分たちだけでやってみたいっていう欲があって企画したんですが、かなり楽しかったので今後も継続していきたいですね。
Vinyl Youthとしての今後の展望等はありますか?
D:Juddyがこの夏からロンドンに留学して、Kinyaもニューヨークにしばらく行く予定なので、その間はKamomeと2人で活動していきたいと思います。
もしかして解散ですか?
全員:それはないです(笑)
Ki:例えば、ニューヨークやロンドンでもVinyl Youthのパーティができたらいいですね。
D:僕は4人が別の場所でも自分のやりたいことを追求して、成長するのは凄く良いことだと考えています。同じクルーだからといって、全員が同じ場所に留まって切磋琢磨する必要はないですし。
Ki:僕やJuddyが海外で感じたことをVinyl Youthにフィードバックして、貢献できたらいいなと思いますね。
D:そういうのは刺激になるよね。
それぞれのこれからの目標を教えてください。
D:僕は楽曲制作を本格的にやっていきたいです。今は既にある曲のエディットをやって現場でかけたりしていますが、ゆくゆくはオリジナルの楽曲を完成させてリリースできればと思っています。
Ka:僕はDaichiほど数を作れてはないんですけど、曲は出したいと考えています。あと、僕は(DJの)現場の数が4人の中だと一番多いんです。しかも尊敬する先輩たちと共演する機会が多いので、そこは彼らから色々と吸収してしっかりこなしつつ、海外のアーティストとも繋がれればと思います。今働いているDOMICILE TOKYOも音楽との繋がりが強いお店なので、そこは大事にしていきたいですね。このお店に関わっているからこそできることも、色々あると思うので。
Ki:個人的な目標だと服を作りたいというのはあるんですが、Vinyl Youthとしては僕は楽しくパーティできればいいかな(笑)。先ほども言いましたけど、海外でのパーティはやってみたいです。
J:僕はまずロンドンに行って、現地で生活して曲を作りたいです。向こうではロックでもダンスミュージックでも現地に根付いている伝統的なカルチャーがあると思うので、それらを実際に体験して自分の根幹を確立させたいですね。ダンスミュージックをやりつつも、しっかり音楽的なバックグラウンドを身に付けたいというか。そして現地でもVinyl Youthのパーティが実現できたら最高ですね。
最後に、パーティの告知等があればお願いします。
D:直近の大きなニュースは、7月22日(金)にOPPA-LAでTodd Terjeを迎えてのサンセットパーティがあります。Vinyl Youthで海外のDJをサポートするのは初めてで、しかも自分たちの思い入れのあるアーティストなので、この話が来たときは嬉しかったですね。
Ka:実はチケットは告知が出てから1日で完売しちゃったんですが……。
D:あとはJuddy渡英前の4人での最後のパーティを、8月10日(水)にOPPA-LAでやる予定です。
和田daaa剛( powboyz / OPPA-LA )(@daaa_enoshima777)がシェアした投稿
Todd Terjeとの共演はひとつ夢が叶ったって事ですね。では今後共演してみたいDJやアーティストはいますか?
Ka:DJ Harveyはもちろんですが、Idjut Boysですかね。
D:僕はLovefingersをVinyl Youthで呼びたいです。あとは僕らが出会ったきっかけでもあるRub N Tugも。
J:僕もIdjut BoysとRub N Tugかな。
Ki:僕は瀧見憲司さんですね。これまで何度か共演したことはあるんですが、Vinyl Youthのパーティに出てもらったことはないので。
D:瀧見さんはヤバいね(笑)。良いタイミングで実現させたいね。
2022 Hypebeast Limited. All Rights Reserved.
利用規約 プライバシーポリシー
HYPEBEAST® is a registered trademark of Hypebeast Hong Kong Ltd.
インタビューや トレンド情報、その他限定コンテンツが満載。
読者に無料で提供する代わりに広告収入を得ています。このサイトをホワイトリストに追加していただけると幸いです
ホワイトリストに追加
既に追加済みですか? ページを更新