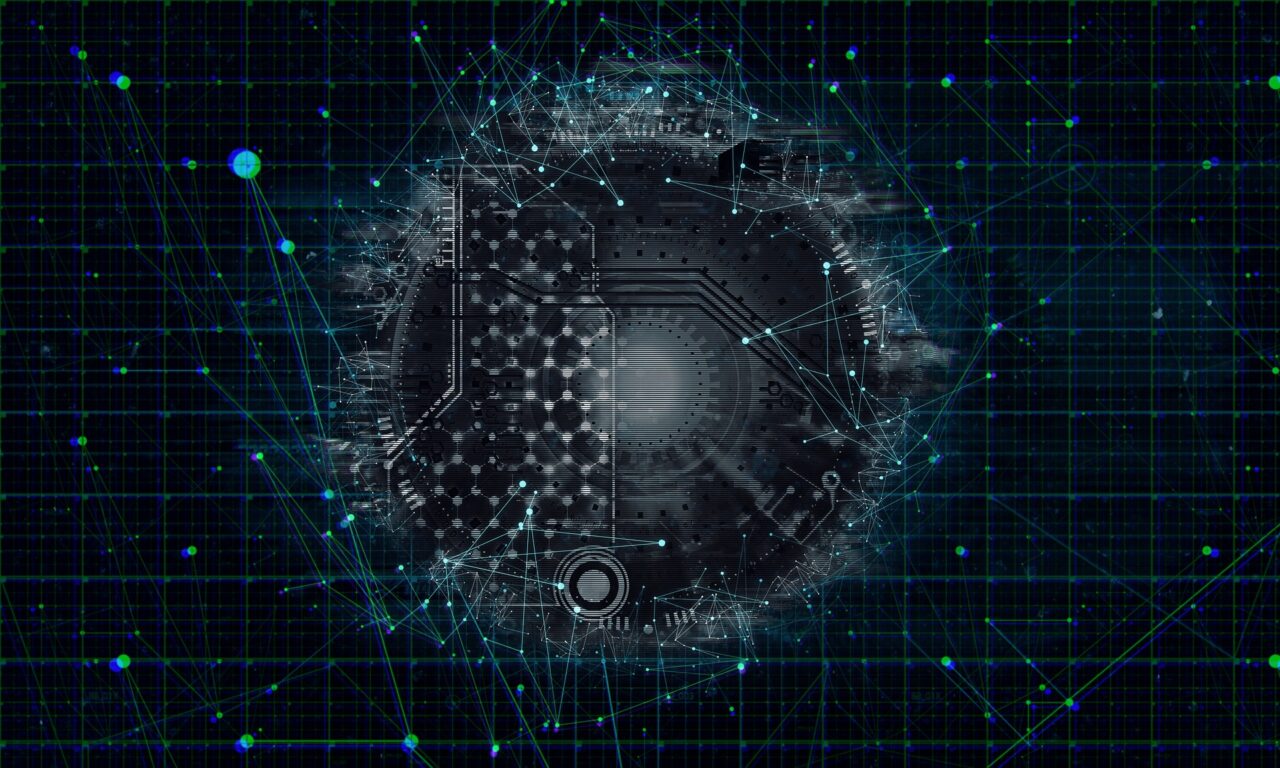KOMPASS話題のキーワード
インタビュー・テキスト by 黒田隆憲 撮影:西村満 編集:黒田隆憲、CINRA.NET編集部
The Beatlesの『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』がリリースされた1967年や、パンク・ムーブメントが勃発した1977年など、ロック・ポップミュージック史にはターニングポイントとなる年がいくつかある。いまからちょうど30年前、数多くの名盤が生まれた1991年もまた「ロック史における重要なターニングポイント」と位置づけることができるだろう。
例えば、1980年代にはずっと「古い」とされていた1960年代ロックを再評価する機運が、1980年代半ばから英国で高まり出し、マンチェスターを拠点とする「セカンド・サマー・オブ・ラブ」と融合。1991年に、Primal Screamの『Screamadelica』やシューゲイザーの金字塔となるMy Bloody Valentineの『Loveless』が産声を上げた。一方、米国シアトルではグランジの先駆けといわれるNirvanaの『Nevermind』がこの年リリースされている。ここ日本でも、そうした海外のムーブメントに呼応するように、たくさんの良質なアルバムが生まれていた。「グランジ元年」や「ブリットポップ前夜」などとも称される1991年。いったいこの年に世界では何が起きていたのだろうか。
2020年9月、その名も『THE THIRD SUMMER OF LOVE』をリリースするなど当時の音楽に大きな影響を受けているシンガーソングライターのラブリーサマーちゃんと、リアルタイム世代であるシンコーミュージック編集者・荒野政寿とともに、1991年を振り返ってみた。
―いまから30年前、1991年って荒野さんは何をしていました?
荒野:ぼくは受験に失敗して浪人1年目。翌年の4月に日大芸術学部に入るまで、高校時代からバイトしていたレコード屋に浪人中も日曜日以外は出ていました。1日7時間くらい働いていたのかな。それで学費を貯めていましたね。
ラブサマ:すごい! えらいですね。
荒野:あははは。バイトが休みの日は渋谷のレコード屋をひたすら回っていました。ぼくらの世代は大抵そうだと思うのですが、まずは全米ビルボードチャートの「トップ40」から入って、そこから自分の好きなジャンルを深掘りしていくという。1980年代後半から90年代初頭にかけて人気があった洋楽の筆頭はユーロビートでしたが、ぼくは「それよりもロックが聞きたい!」と思った。それで以前から好きだったThe Beatlesをはじめ1960年代の音楽に影響を受けた、UKとUSのインディーにどんどん興味が湧いていきました。
荒野:例えばUSだとThe Three O’ClockやRain Paradeのような、いわゆる「ペイズリー・アンダーグラウンド」周辺が大好きでしたね。UKでは、それらと近い匂いがするCreation Recordsのアーティストや、C86(英国の音楽雑誌NMEが1986年にリリースした伝説のコンピレーションカセット)周辺のバンドなどを好んで聴くようになりました。なかでも世代的に大きかったのが、1989年にリリースされたThe Stone Roses(以下、ローゼズ)の1stアルバムです。
ラブサマ:邦題は『石と薔薇』だったんですね。
荒野:ものすごい直訳タイトルですよね(笑)。今回、あらためていろいろ聞き直してみて、ローゼズの影響下にあるUKインディーバンドはこんなに多かったんだなと再認識しました。特にリズムです。1stアルバムの前にリリースされた“Elephant Stone”や、その後にリリースされる“Fools Gold”(1989年『Fools Gold / What the World Is Waiting For』収録)など16ビートを強調したファンキーなリズムを、みんなこぞって取り入れていた。
ラブサマ:Blurの“There’s No Other Way”なんて、もろにそうですよね。
―ラブサマちゃんは、1991年ってどんな印象がありますか?
ラブサマ:ロックミュージック史のなかで、「ブリットポップ元年」といわれているのが1995年(Oasisの“Roll With It”とBlurの“Country House”が同じ日にリリースされた年)じゃないですか。そこが私にとって一番興味のある時代なので、1991年はその「前夜」というイメージがいままではありました。でも、今回の対談のお話をいただいていろいろ調べてみたら、めちゃめちゃ豊作の年なんですよね。
ラブサマ:私、Blurの1stアルバム『Leisure』が大好きなんですよ。この頃はまだグレアム・コクソン(G)のローファイっぽいギターなど、メンバーそれぞれの持ち味はさほど生かされていないんですけど、それでもデーモン・アルバーン(Vo,G)のシニカルな歌詞や、キャッチーだけど一筋縄ではいかないメロディー、プログレっぽい変拍子のようなひねりも効いているし。
―“Birthday”とかは、シド・バレットっぽさもありますよね。
荒野:当時のデーモンは金髪でマッシュルームっぽくて、映画『時計じかけのオレンジ』のアレックス(マルコム・マクダウェル)みたいないで立ちだと思いました。優等生というよりは、知能犯的な感じ……この人絶対に天才だなと思っていましたが、当時はUKインディー通の仲間にBlurが好きだと言うと「正気かよ、あんなバンド亜流だろ」って散々バカにされました(笑)。
ラブサマ:ええー! そうだったんだ……あんな名盤なのに。
―当時はいいとこ取りのハイプなバンドと思われていたフシもありましたよね。のちのブリットポップにつながる「シックスティーズ再評価」の機運は、1991年にはかなり高まっていました。ローゼズしかり、Inspiral CarpetsやCharlatansのような、The Doorsを彷彿とさせるオルガンロックしかり、みんな1960年代のロックに影響を受けたバンドです。
荒野:Creation Records周辺を見渡してみても、Primal Screamも初期はThe Byrdsのような12弦ギターを使ったフォークロックをやっていたし、のちにアシッドハウスへと傾倒していくThe Timesも、もともとはTelevision Personalities周辺から現れたネオモッズバンドだった。ちなみにアラン・マッギー(Creation Recordsの創始者)は、さっき話したRain Paradeとも契約しようと思っていたみたいですね。当時のUKの「シックスティーズ再評価」は、USのペイズリー・アンダーグラウンドから受けた影響がものすごく大きかったと思う。
―ペイズリー・アンダーグラウンドの話は、以前ラブサマちゃんと別の対談で少ししたことがあるのですが(参考記事:ラブリーサマーちゃんと学ぶ、「現実逃避の音楽」ドリーム・ポップの歴史)、あらためてどんなムーブメントだったかを荒野さんの視点からお聞かせいただけますか?
荒野:Jellyfish(アメリカのパワーポップバンド)のジェイソン・フォークナーが、もともと所属していたバンドがThe Three O’Clockで、彼らやThe Bangles、The Dream Syndicateなど、1960年代サイケに影響を受けたバンドを中心とする1980年代前半から始まったLAのシーンです。例えばThe Three O’Clockは、「カルフォルニアのネオモッズ」という感じのイメージをプロモーションビデオでも打ち出していました。プリンスのようなアーティストも注目していて、のちに彼が設立したレーベルPaisley Parkからアルバムを出すなどしていたんですよ。
ラブサマ:へえ、プリンスも!
荒野:当時、日本では六本木にあった大型レコード店「WAVE」が、このあたりのバンドをすごく推していました。Rain ParadeとThe Dream Syndicateのツーマンで、1984年に渋公(渋谷公会堂:現在のLINE CUBE SHIBUYA)でライブをやったんですよ。THE COLLECTORSの加藤ひさし(Vo)さんがこれを観てるんですけど、「客席はガラガラだったし、演奏もうまくなくて期待していた感じと違った」とおっしゃっていましたね(笑)。
でも、そういう「シックスティーズ再評価」のようなムーブは、1980年代半ばから世界のインディーレベルで同時多発的に起こっていたのかもしれない。XTCの変名プロジェクト、The Dukes of Stratosphearの1stアルバム『25 O’Clock』がリリースされたのも1985年ですから。
荒野:ちなみにプリンスは1991年に、『Diamonds and Pearls』というアルバムを出しています。彼にとっては「仕切り直し」の時期といいますか。バンドの編成も変えて、当時台頭してきたヒップホップにも対応しようとしている。プリンスはコクトー・ツインズも好きなんですけど、そういう耽美的な要素がこのアルバムではファンクやヒップホップなどとごちゃ混ぜになっていて面白いんですよ。
ラブサマ:そうだったんですね。プリンス、ちゃんと聴いたことないので聴いてみます。
―「シックスティーズ再評価」が同時多発的に起こっていたという意味では、ペイズリー・アンダーグラウンドとはまた別の潮流でR.E.Mやレニー・クラヴィッツという存在もありました。まずR.E.M.の『Out of Time』は1991年のアルバムです。
荒野:R.E.M.は解散してから長い時間が経っていて、その間メンバーも華やかな活動をしていないせいか、最近は彼らの作品が若い人たちにどう受け止められているのかよくわからないところがあって。ラブサマちゃんはどうですか?
ラブサマ:周りで聴いている人はあまりいないです(笑)。私もたまに聴いて「いい曲だなあ」と思うし好きですけど、熱心に聴いてきたわけじゃないですね。
荒野:やっぱり、不在期間が長過ぎたのかも知れない。フォークロック的なスタイルは初期から一貫していて、時期によってマイナーチェンジはあるけど、基本的な音楽スタイルはずっと一緒だったから、そのぶん取っつきにくく見えそうな気はしますね。もはや、R.E.M.が武道館でやったことなど知らない人のほうが多いんじゃないかな。
ラブサマ:え、武道館でやったの? すごいじゃないですか。
ラブサマ:その流れでいうと、同じく1960年代ロックに影響を受けたVelvet Crushの『In the Presence of Greatness』も、いま聴いてもまったく古びてないですよね。私、このアルバムが本当に好きなんですけど、これってじつはデモテープだとか。
荒野:そう。メンバーは出すのを渋っていたらしいけど、アラン・マッギーが「この荒削りな音がいいんじゃん!」と言って、録り直させなかったらしいです。個人的にはこのアルバムと、これをプロデュースしたマシュー・スウィートの『Girlfriend』、それからTeenage Fanclubの『Bandwagonesque』が同じ1991年に出ているだけでもう、1991年はとんでもない年だなと思いますね。
荒野:特にマシューの『Girlfriend』は、いまラブサマちゃんが出してくれたVelvet Crushの『In the Presence of Greatness』とレコーディングメンバーも被っているし、切っても切れない印象です。特筆すべきは、リチャード・ロイド(Television)とロバート・クイン(リチャード・ヘル&ザ・ヴォイドイズ)というレジェンドが参加していたこと。そのときの旬のミュージシャンを核に、新旧の世代がつながっていろんな作品が生まれていくことにワクワクしました。世代的には少し上のドン・フレミングが、Dinosaur Jr.のシングルや、Teenage Fanclubの『Bandwagonesque』に関わったりしていたのもそう。
―レニー・クラヴィッツ(以下、レニクラ)はどうですか。1989年に1stアルバム『Let Love Rule』が出たときの衝撃は計り知れなかったし、本国と同じくらい日本での人気も高かったですよね。小林武史さんがレニクラのスタジオで、Mr.ChildrenやYen Town Bandのレコーディングをしたのは有名な話です。
荒野:レニクラは1991年だと『Mama Said』を出していますね。いまは過小評価されているけど、ぼくはこれが出たときめちゃめちゃ聴いたし、彼とポール・ウェラーの影響で、カーティス・メイフィールドなどのソウルミュージックもちゃんと聴くようになったんですよ。このあとのネオソウル勢に与えた影響も絶大でしょう。それと同時に、同じくこの年『Use Your Illusion I』『II』を発表したGuns N’ Rosesのスラッシュが参加していたり、音楽性の幅がとても広い。
―当時レニクラは「黒いジョン・レノン」ともいわれていて、『ジョンの魂』(1970年にリリースされた、ジョン・レノンの初ソロ作)をシミュレートしたような1stアルバム『Let Love Rule』(1989年)のサウンドも衝撃的でしたね。
―一方、UKでは「シックスティーズ再評価」と「セカンド・サマー・オブ・ラブ」(1980年代後半に英国で起きたダンス・ミュージックのムーブメント)が融合し、Primal Screamの『Screamadelica』やMy Bloody Valentine(以下、マイブラ)の“Soon”(1990年)などが生まれました。
荒野:“Soon”が収録されたマイブラの2ndアルバム『Loveless』はもちろん孤高の名盤なんですけど、「1991年の名盤」として代表的に挙げていいのか迷うところなんですよ。ほかのどの作品とも違うし、とにかくサウンドがヘン!(笑)
―『Loveless』は、1989年には原型ができ上がっていたものの、オーバーダビングやミックスダウンに2年もかかったといわれています。「1991年っぽさ」を感じないのは、そういう制作過程があったからなのかもしれないですよね。
荒野:だから当時聴いたときも、スッとは入ってこなかった。前作『Isn’t Anything』(1988年)に比べるとあまりにも奇妙で……。アルバム1枚で1曲みたいに感じる塗り壁のようなサウンドだったし、“Soon”のようなダンサブルな楽曲がもっと入っているのかなと思って心の準備をしていたら、意外とそうでもないし。
―たしかに。セカンド・サマー・オブ・ラブの象徴のようなPrimal Screamの『Screamadelica』に対して、マイブラはどんな返答をするんだろう? という期待はあったかもしれない。なのに、かなりアンビエントにシフトしていて驚きましたよね。
ラブサマ:私、『THE THIRD SUMMER OF LOVE』というアルバムをつくったくらい、当時のシーンが大好きなんですけど、その存在を知ったのはPrimal Scream『Screamadelica』のおかげなんですよ。最初に彼らを認識したのは“Ivy Ivy Ivy”(1989年)ですが、ああいうガレージロックや1枚目の『Sonic Flower Groove』(1987年)みたいなフォークロックを奏でていた人たちが、『Screamadelica』であそこまで覚醒したことに、すごく憧れを感じます。
荒野:でも『Screamadelica』を聴いたときも、びっくりしたのを覚えてますよ。先行シングルの“Come Together”(1990年)がぼくはすごく好きで「ジム・ビーティーがいなくてもこんないいメロディーが書けるんだ!」と感動してアルバムを買ったら、まったく違う、ほぼインストバージョンの“Come Together”が入ってて。「歌、ねえじゃん!」って(笑)。
ラブサマ:あははは! ボビー・ギレスピー(Vo)が歌えばどんな曲でも名曲になるのに、あそこまでダンスミュージックへ舵を切ったガッツはすごいですけどね。
荒野:きっとアンドリュー・ウェザオール(イギリスのDJ、プロデューサー。2020年2月17日に逝去)の影響もデカかったと思うけど、それまでロック一辺倒だったぼくがこの作品の真価を理解するには、ちょっと時間が必要でしたね。
荒野:関係ないけど、この頃のサウンドでいうとワウペダルの存在感ってすごくないですか? みんなワウペダルを踏んでいましたよね。
ラブサマ:わ、たしかに!
荒野:ぼくはローゼズのジョン・スクワイアが発端かなと思っているんだけど、BlurもChapterhouseもRideも、みんなギターにワウをかけてます。きっと、16ビートのリズムとロック的なものをどう絡ませるか?というときに、ワウが便利だったのかも知れないですね。
―ダンスミュージックでいうところの、フィルター的な使い方もワウでできますし。
荒野:そうそう。ワウペダルは1960年代後半、ジミ・ヘンドリクスやCreamなどが用いて脚光を浴びたけど、やっぱり飛び道具的なエフェクトなので、1980年代になるとロック界隈ではほとんど誰も使わなくなる。しかし1990年代になってダンスとロックが融合し、メロディーだけじゃなくて「ビートやリズムとどうつき合っていくか?」ということを考えたときに、再びワウペダルが重要になっていったのだと思います。ローゼズの“Fools Gold”なんてワウギターだらけですよね(笑)。
ラブサマ:なるほどね。すごく面白いです。
荒野:そういえば、当時多くのミュージシャンやライターが1991年のベストアルバムの1枚に選んでいたFive Thirtyの『Bed』も、ワウを踏みまくってる。このアルバム、最高なんですよ。普通のエイトビートの激しい感じのロックもあれば、ローゼズタイプの“13th Disciple”というダンスっぽい曲もあるし、サイケポップっぽい“You”という曲もあって。
ラブサマ:Five Thirty、知らなかったです。気になる。
荒野:ギター(ポール・バセット)もベース(タラ・ミルトン)もリードボーカルを取れるし曲も書けるのだけど、そういうリーダー格が複数いるバンドって解散するのが早いじゃないですか(笑)。彼らもすぐに仲違いして、それぞれ別のバンドをはじめたんです。
―そのせいか、いまやほぼ忘れ去られています。
荒野:勿体ないですよね。ちなみにドラマーの人(フィル・ホッパー)は、日本に移住してN.G.THREEなど日本のバンドでもプレイしてました。
ラブサマ:え、そうなんですか。私ともバンド組んでほしい!
―当時の社会情勢については、荒野さんはどんなことを覚えていますか?
荒野:一番大きかったトピックはやはり湾岸戦争の勃発とソビエト連邦の崩壊ですよね。時代が大きく変動しているのを実感した年です。そういえば、今年リリースされたBreachersの新作『Take the Sadness Out of Saturday Night』の1曲目が“91”というタイトルで、まさに湾岸戦争のことを歌っていました。Breachersのリーダー、ジャック・アントノフ(テイラー・スウィフトやロード、ラナ・デル・レイなどを手がけるプロデューサー)は1984年生まれだから、彼が7歳のときの出来事になるのかな。
あとはフレディ・マーキュリーがエイズであることを公表し、その翌日に亡くなったのも1991年なんですよね。
ラブサマ:翌日だったんですか……?
荒野:以前から「具合が良くない」という噂は伝わってきていたんですけどね。現役のロックスターが不治の病で亡くなるというニュース、それまではほとんどなかったから、そういう意味でも衝撃的でした。
―日本では「バブルが崩壊した」といわれて、でもまだ何となく世の中は浮ついた空気が続いていましたよね。ジュリアナ東京がオープンしたのも1991年だし。当時のヒットチャートを見ると、小田和正の“Oh! Yeah! / ラブ・ストーリーは突然に”や、CHAGE&ASKAの“SAY YES”、KANの“愛は勝つ”に槇原敬之の“どんなときも。”など、J-POPクラシック目白押しです。
荒野:音楽業界はまだまだ潤っていましたよね。「小室ブーム」の全盛期は1996年からですし。いわゆる「プロデューサー時代」が訪れる少し前の時代。小林武史さんが原由子の2枚組ソロアルバム『MOTHER』のプロデュースをしたり、彼が作編曲した小泉今日子の“あなたに会えてよかった”が大ヒットしたりしたのが1991年で、やがてサザンオールスターズ関連以外のアーティストも積極的に手掛けるようになっていく。
ラブサマ:そうなんですね。その頃はもうMr.Childrenも活動しているイメージがあったけど。
荒野:小林さんがMr.Childrenを手がけるのは1992年なんです。
―ちなみにラブサマちゃんは、当時の日本の音楽だとどの辺りが好きですか?
ラブサマ:Venus Peterの『SPACE DRIVER』(1992年)とかめちゃめちゃ聴きました。あとはスピッツですね。
―スピッツの同名1stアルバムと、2ndアルバム『名前をつけてやる』も1991年リリースです。後者は当時マイブラやRideに傾倒していた草野マサムネさん(Vo,G)が、「ライド歌謡」をテーマにUKのギターロックのサウンドと歌謡曲を融合しながらつくったアルバムといわれています。
ラブサマ:そうだったんだ! いま聴くと全然Rideには聴こえないけど(笑)、やっぱりあの人たちは「歌心」ですべて持っていっちゃうんですね。1991年だと、あとはCHARAさんの1stアルバム『Sweet』も大好きです。
荒野:プロデューサーの浅田祐介さんと一緒にやっていた頃ですね。
ラブサマ:音がモダンでいまも聴けちゃう。いい曲ばっかりなんですよ。歌詞と歌声が、女性というより「女の子」という感じ……愛への眼差しがまだ無邪気すぎるし、しかも切ない歌詞が多くて「これぞ1stアルバム!」という感じ。“うそつくのに慣れないで”や、“Heaven”“Sweet”“Break These Chain”など、大好きな曲ばかり入ったアルバムです。
―そして、1991年の音楽シーンについて語るうえで、避けては通れないのがNirvanaの『Nevermind』です。このアルバムのリリースをきっかけに、あっという間に彼らはシーンを席巻した印象が当時はあったのですが、荒野さんはどう見ていましたか?
荒野:ぼくが最初に彼らの存在を知ったのは、雑誌『CROSBEAT』に掲載されていた「ソニック・ユースが選ぶオールタイム・ベスト50アルバム」というコーナーでした。The StoogesやThe Velvet Underground、Televisionらの名盤が並ぶなか、見たことがないレコードジャケットが掲載されていたんですよ。それがNirvanaの1stアルバム『Bleach』(1989年)だったんです。
ラブサマ:そんな企画が雑誌に載っているのもすごいですね。
荒野:当時もちょっとした話題になりましたよ。このページを同級生が見せてくれて、持ってないアルバムを競ってチェックしていく感じでした。でもこの時点では、仲間うちで誰も『Bleach』を聴くことができなくて。そうこうしているあいだに“Smells Like Teen Spirit”がラジオで流れはじめました。最初はピンとこなかったんですよね。「これ……メタルじゃね?」って(笑)。それまでSonic YouthやPixiesなど、一風変わったアートっぽくてモダンな音楽がUSで生まれてUKにまで影響を及ぼしていたのに、またメタルっぽいリフの時代に逆戻りするの!? と思って。
荒野:ぼくはオルタナを聴く前にメタルも聴いていたので、余計にそう思っちゃったんですよね。逆にMetallicaがこの年出した『Metallica』(通称「ブラック・アルバム」)で急にオルタナっぽくなったのも、不思議な感じがしました。
ラブサマ:じつは私も、最近までちゃんとNirvanaを聴いたことがなかったんです。以前、大好きなThe Vaselinesのカバーを彼らがやっていたのですが、“Molly’s Lips”はまだしも“Son Of A Gun”のアレンジがどうも受けつけなくて……(笑)。父がハードロックキッズだったんですけど、その反発で私はアノラック(The VaselinesやThe Pastelsなど、主にグラスゴーの「ヘタウマ」と呼ばれたギターバンドの総称)などを聴いていたので、余計に違和感があったのかもしれないです。でも、今回のお話を機会にちゃんと聴いてみたら、“Lithium”とかめちゃめちゃいい曲だったのでびっくりしました。
荒野:1991年はNirvanaを筆頭に、USインディーのアーティストがどんどんメジャーへいくんですよね。Pearl Jamも、Dinosaur Jr.もそう。おそらくそれは、前年にSonic Youthが『Goo』(1990年)でメジャーデビューしたことも大きかったと思うんですけど。
―Sonic Youthのメジャー移籍は当時ちょっとした「事件」でしたよね。ただ、『Nevermind』からはじまったグランジブームもあっという間に収束してしまった。
荒野:結局「グランジ」って、音楽スタイルというよりはファッションワードとして消費されてしまった感はありますよね。同じシアトル出身ということで、NirvanaもPearl JamもSoundgardenも「グランジ」で括られていましたけど、やってることはまったく違っていたし(笑)。
荒野:しかも『Nevermind』の翌年にはキャメロン・クロウ監督が『シングルス』という、シアトルを舞台にした青春映画をつくるんですよ。サントラにはクリス・コーネル(Soundgarden)やMudhoney、Alice In Chainsなんかが参加していて。めちゃめちゃ商業的なプロジェクトにみんな飲みこまれていくのを目の当たりにした気分になりました。
ラブサマ:そんな映画があったんですね。ちょっと見てみたいです。
荒野:いま見たら面白いかもしれない。主演のマット・ディロンが、グランジファッションで終始ダラダラしてるだけの映画ですが(笑)。ただ、そういう消費のされ方をすると、文化としてはあっという間に萎んじゃうんだなということを痛感します。
―1994年4月5日にカート・コバーン(Vo,G)が亡くなったときはどう思いました?
荒野:立ち直れないくらい落ち込みました。しばらくロックが聴けなくなりましたね。さっき話したように、Nirvanaはぼくもラブサマちゃんと同じで最初ピンとこなかったんですけど、だんだん好きになっていったんです。その頃はもう『Bleach』も聴いていたし、“About A Girl”のようなポップな曲があることも知った。インタビューを読むと、カートは少年ナイフの大ファンだったりするじゃないですか。
ただ、3rdアルバム『In Utero』(1993年)をリリースするちょっと前くらいから、“I Hate Myself And Want To Die”のような自殺をほのめかすような曲も出していて。『In Utero』には“Rape Me”なんて曲もあるし、「この人大丈夫かな」「いよいよヤバイんじゃないか?」と思ってたら本当に死んでしまった。その頃はもう、同世代の代表的なアーティストとなっていたし、亡くなったときの喪失感は本当に大きかったです。
ラブサマ:そうだったんですね。
荒野:当時は海外の音楽メディアがカートに対してめちゃくちゃ意地悪だったんですよ。何かあるたびに彼の言動を叩いたり、コートニー・ラヴとつき合うようになると、今度はセットでバカにしたりして。そういうことがずっとあって、それに対する反感も作品に落とし込んでいて……そんな一連の流れも含めてハラハラしていたんですよね。「早く彼を休ませてあげなきゃ、どうにかなってしまうんじゃないか?」って。だんだん弱っていく過程を雑誌で逐一見ているような感じにもなっていました。
もしNirvanaがGeffinのような大手レコード会社へ行かず、Sub Popに残ったままMudhoneyくらいの規模で続けていたら、おそらくまだ生きていたかもな……とかいろいろ想像してしまいます。
―そろそろお時間になりました。今回、1991年を振り返ってみるという企画でしたが、ラブサマちゃんいかがでしたか?
ラブサマ:こうやって荒野さんのお話をうかがっていくと、1991年はやはり実り多い年だったのだなということがよくわかりました。自分がずっと好きだった作品がいろいろつながっていることもわかったし、いままで知らなかったアルバムや楽曲もたくさん教えてもらえたので、ますますサブスク巡りが楽しめそうです。今日はありがとうございました。
荒野:こちらこそ!
2020年9月16日(水)発売
価格:3,630円(税込)
COCP-41239
1. AH!
2. More Light
3. 心ない人
4. I Told You A Lie
5. 豆台風
6. LSC2000
7. ミレニアム
8. アトレーユ
9. サンタクロースにお願い
10. どうしたいの?
11. ヒーローズをうたって
2021年8月12日(木)発売
著者:黒田隆憲、佐藤一道(共同監修)
価格:3,080円(税込)
発行:シンコーミュージック
1988年から都内のレコードショップで勤務。1996年、シンコー・ミュージックに入社。『WOOFIN’』『THE DIG』編集部、『CROSSBEAT』編集長を経て、現在は書籍と『Jazz The New Chapter』『AOR AGE』などのムックを担当。著書に『プリンスと日本 4 EVER IN MY LIFE』(共著、小社刊)。今年8月、『シューゲイザー・ディスク・ガイド revised edition』を編集。
1995年生まれ、東京都在住の26歳女子。2013年夏より自宅での音楽制作を開始し、インターネット上に音源を公開。SoundCloudやTwitterなどで話題を呼んだ。2015年に1stアルバム『#ラブリーミュージック』、2016年11月にはメジャーデビューアルバム『LSC』をリリースし好評を博す。2020年9月には待望の3rdアルバム『THE THIRD SUMMER OF LOVE』を発売。可愛くてかっこいいピチピチロックギャル。
シェアする
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
新たな発見や感動を得ることはできましたか?
カネコアヤノと曽我部恵一、小田朋美が語る「猫と聴きたい曲」
小西遼ソロプロジェクト・象眠舎が探求する、人間が変容する感動
握手会モデルの崩壊で向き合う アイドルセルフプロデュースの時代
ピーター・バラカンと高橋健太郎が語る『アメリカン・ユートピア』。再上映を機にその魅力を探る
サカナクション山口一郎「CDを100万枚売って、音楽史に名前を残す時代は終わった」
元ブクガの矢川葵が堂島孝平と語る、昭和ポップスの魅力。80'sアイドルを現代に継承する理由
ピーター・バラカンと高橋健太郎が語る『アメリカン・ユートピア』。再上映を機にその魅力を探る
TK from 凛として時雨が語る、B'z稲葉浩志との共作「この瞬間を一生覚えておく」